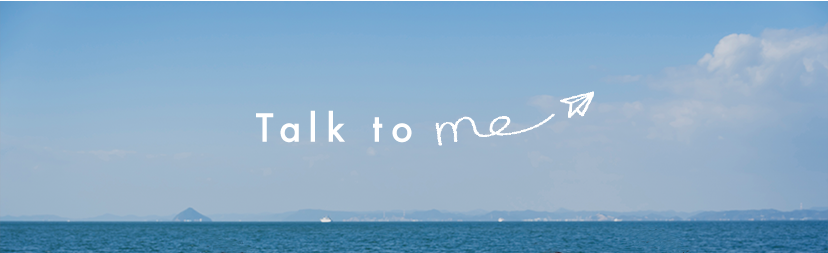生前贈与
不動産の生前贈与(名義変更)
- 不動産を今のうちに次の世代に移したい
- 相続税対策をしたい
- 相続人以外の人に財産を渡したい
- 生前贈与はお得なの?
- 子供が家を建てるので土地をあげたい
そんなときは生前贈与です。
私が思う生前贈与の素晴らしいところは
まず、自分の意志で 好きな人に、好きな時に、好きなだけ 贈与できるというところ。
もう一つ素晴らしいのが、
自分が生きているときにあげるので、もらった人が笑顔になれるのを見られる、ありがとうと言ってもらえるというところ。
相続だと亡くなったときに、全財産が承継されるのでタイミングが選べません。
亡くなった後なので喜んだ顔も見れません。
そう考えると贈与って素敵です。贈与税がちょっと気になりますが…
このページではそんな素敵な生前贈与に関することをご案内します。
私たちがお手伝いできること
生前贈与の登記手続きだけでなく、他の制度とも比較したプランニング、贈与税に関して税理士と連携した対応など贈与の先にある願いを大切にします。
| 生前贈与の プランニング |
手続き | 贈与税 |
|---|---|---|
|
|
|
生前贈与のポイント
- 書面にする
将来のトラブルを防ぐためにも、贈与契約書を作成することが大切です。 - あげたら戻ってこない
一度贈与してしまうと戻ってきません。やっぱり返して。とならないように気を付けましょう。 - やっぱり気になる贈与税
贈与税については事前にしっかり検討することが大切です。
贈与税に関する非課税制度
贈与税に関しては様々な非課税制度が用意されています。贈与税は改正が多いため中途半端な知識では危険です。私たちは、税理士と連携し、税金を含めた費用負担が最小限になる方法をご提案します。
- 暦年贈与
年間110万円までの非課税枠があり、長期で贈与を続けていくと、自分の財産を減らすことができるため相続税対策にもなります。 - 相続時精算課税制度
60歳以上の祖父母または両親から、18歳以上の孫または子へ2500万円までの贈与であれば贈与税がかからないという制度です。その後、相続が発生した時に贈与を受けた財産を相続財産に加算して相続税を計算します。 - 配偶者控除の特例
婚姻期間が20年を超える夫婦に適用されます。2000万円の基礎控除があり、居住用の不動産であれば贈与税が非課税となります。 - 住宅取得資金贈与
祖父母または両親から、自己の居住用不動産の新築等の資金として金銭の贈与を受けた場合、一定額について贈与税が非課税となる制度です。
生前贈与手続きにかかる費用
| 業務内容 | 報酬額(消費税別) | 実費 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 贈与による所有権移転(不動産を取得する人ごとの金額) | 1筆 42,000円 | 登録免許税 固定資産税評価額の2.0% |
報酬-1筆増えるごとに2,000円加算 |
| 登記原因証明情報・贈与契約書作成 | 20,000円 ~40,000円程度 |
収入印紙代200円 | 不動産の数や、内容に応じて変動します。 |
| 完了後の謄本 | 1,000円 | 1筆 480円 | |
| 登記情報閲覧 | 1,000円 | 1筆 332円 |
ご相談の流れ
1初回相談予約(初回相談無料)
2打合せ・概算費用の提示
相続人や相続財産、お客様のご希望ついてお伺いします。
手続きに関する概算費用をお伝えします。

3ご依頼
手続きについてのご説明・報酬について納得いただけましたら手続きに入ります。
4登記関係書類、贈与契約書の作成押印
ひろせ司法書士法人が贈与契約書、登記関係書類など必要な書類を作成します。
5登記関係書類、贈与契約書の署名押印
作成した贈与契約書等に署名押印(※押印は実印)をします。
贈与者(あげる人)受贈者(もらう人)お二人でお越しください。
6法務局へ登記申請
ひろせ司法書士法人が法務局に登記申請を行います。
7必要に応じて贈与税の申告
贈与税の申告が必要な場合は税理士をご紹介いたします。
必要書類
-
贈与者(あげる人)
印鑑証明書・実印・身分証明書(免許証・保険証等)権利証(登記済証・登記識別情報) -
受贈者(もらう人)
住民票・認印・身分証明書(免許証・保険証等) - 固定資産税の納税通知書又は固定資産税評価証明書
初回相談無料
お気軽にお問い合わせください
オンライン相談も承ります!