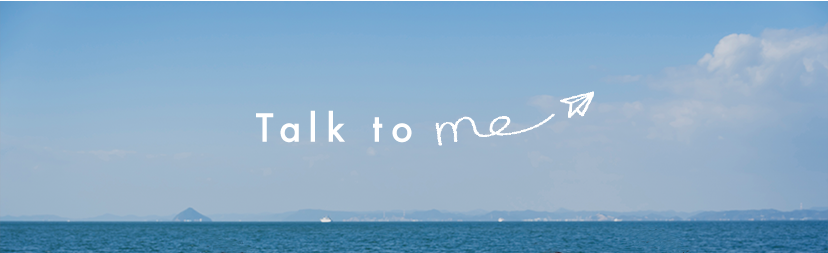ひろせ日記
病院で遺言を作れますか?死亡時危急遺言という制度
相続の相談なら香川県高松市の「ひろせ司法書士・行政書士事務所」廣瀬修一です!
相続のご相談を受けていると、よくあるこんなお話。
- 相続人同士で遺産をどう分けるかでもめてしまった
- 話し合いが長引き、相続税の申告や登記手続きが遅れてしまった
- 相続人の中に連絡が取れない人がいて相続手続きが進まない。
特に、不動産やまとまった財産がある場合は、遺言がないことで大きな混乱を招きます。
実際のケース―死亡時危急遺言で救われたご家族
Aさん(仮名)は病気で余命宣告を受け、ご家族と一緒に当事務所に相談に来られました。
相続人の中に、連絡が取れない方がいて相続手続きが難航する可能性が高い状況です。
「どうしても遺言を残しておかないと相続で困る」
この時のAさんはまだまだお元気そうで、公正証書遺言を作成するために公証役場と日程を調整していました。
※公証役場との日程調整って空き枠が少なくて、意外と時間がかかります。
ところが予定日の前に病状が悪化。
病院からも「今週末が山かもしれない」と告げられました。
病院での「死亡時危急遺言」
このままでは遺言が間に合わない――。
そこで私たちは 「死亡時危急遺言」 の作成を提案しました。
病院の一室で、医師を含む証人3名の立会のもと、Aさんは最後の力を振り絞ってご自身の意思を述べられ、私が遺言内容を書き取りました。Aさんに内容を確認してもらい証人がその場で署名押印。
まさに緊急の場面でしたが、法律に則って無事に遺言を残すことができました。
遺言があったからこそ無事に手続きが進んだ
残念ながらAさんはその後お亡くなりになりました。
しかし、遺言があったおかげで、相続人同士の争いは起きず、相続登記や預貯金の解約もスムーズに行えました。
もし遺言がなかったら――
行方不明の相続人を探し出して連絡をとったり、遺産の分割方法で話し合いがもつれ、手続きが長期化していた可能性があります。
死亡時危急遺言を知っていたこと、そしてその場で行動できたことが、ご家族を救いました。
死亡時危急遺言とは?(詳しく解説)
民法に定められた「緊急時の遺言方法」
死亡時危急遺言(しぼうじききゅういごん)とは、病気や事故などで死期が迫り、公正証書遺言を作成する時間がないときに認められる特別な遺言方法です。
根拠は民法976条で、次のように定められています。
- 遺言者が死亡の危急に迫ったとき
- 証人3人以上の立会いが必要
- 遺言者が口頭で意思を述べ、それを書き取って署名押印する
つまり、病院や自宅でも、証人がいればその場で遺言を残すことができる制度です。
作成の手順
- 遺言者が口頭で内容を伝える
「自宅の土地は長男に相続させたい」「預金は妻に渡したい」といった内容を明確に述べます。 - 証人の一人が筆記する
遺言者の言葉を正確に書き取り、遺言書を作成します。 - 証人全員が署名押印する
証人3人全員の署名・押印が必要です。 - 家庭裁判所での確認申立て
作成から20日以内に、家庭裁判所に「確認の申立て」をしなければ効力を失います。
有効となる条件と制限
死亡時危急遺言には、以下のような条件と制限があります。
- 証人3人が必要
遺言者の親族や利害関係者が証人になると、後で争いの原因になる可能性があります。なるべく中立の立場の人を証人にすることが望ましいです。 - 家庭裁判所の確認が必須
申立てをしなければ無効です。専門家に依頼すれば申立書類の作成もスムーズです。 - 回復後6か月以上生存すると無効
危急時に作った遺言は、遺言者が回復して6か月以上生存された場合は効力を失います(民法976条但書)。
つまり、緊急時の「つなぎ」の遺言であり、体調が落ち着いたら公正証書遺言(または自筆証書遺言)に作り直す必要があります。 - 死亡後に「検認の申立て」が必要
確認手続きが済んだ後、通常の自筆証書遺言と同様に、家庭裁判所で「検認の申立て」を行う必要があります。
検認は、遺言の存在と内容を相続人に周知し、偽造や変造を防ぐための手続きです。
メリットとリスク
メリット
- 公証役場に行かなくても作れる
- 自筆証書遺言を書く力が残っていなくても作成できる
- 病院や自宅でその場で対応可能
- 「とにかく今すぐ遺言を残したい」という状況に対応できる
リスク・注意点
- 証人がすぐに集まらないと作成できない
- 家庭裁判所での確認を怠ると無効になる
- 記録が不十分だと「本当に本人の意思か」が争われやすい
- 危急時の遺言なので、回復してから6か月以上生存すると効力がなくなってしまう
どんなときに使える?
- 入院中に病状が急変したとき
- 公証人を呼ぶ時間がないとき
- 災害や事故で死期が迫ったとき
実際、病院で医師や専門家が立ち会って作成するケースが多くあります。
専門家に相談するメリット
死亡時危急遺言は、あくまで「緊急避難的な手段」です。
その場で作れても、形式不備や証人の不適格によって無効になるリスクがあります。
司法書士や弁護士などの専門家に相談すれば、
- 適切な証人の手配
- 書き取りのサポート
- 家庭裁判所への申立て
まで含めて、確実に遺言が効力を持つようにサポートできます。
まとめ
- 死亡時危急遺言は、死期が迫ったときに使える「最後の遺言方法」
- 証人3人、家庭裁判所での確認、6か月ルールに注意
- あくまで緊急時の手段なので、回復したら公正証書遺言に作り直すことが必要
「遺言を作りたいけれど体調が心配」「病院でも遺言はできるの?」と不安な方は、ひろせ司法書士事務所にご相談ください。
いざというときに備え、安心して大切な財産を次の世代に残すためのお手伝いをいたします。
初回相談無料
お気軽にお問い合わせください
オンライン相談も承ります!